まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter66_宝石の描き方。
主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。
*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より
また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。
後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。
半透明な物体、宝石を例に練習しよう。透明な物質を描く方法を前提として説明する。半透明な物体を描く時は透明なときと順番は同じだ。光の屈折について。光の屈折について簡単に説明すると、半透明な物体に光が入射したときに光の方向性が曲がる。しかしここでは視覚的に解釈するに留める。写真を見るとカップの中にある紅茶に床の台が歪んで映り込んでいる。透過光が透明な物体の形によって歪んでできている。このように半透明の物体に光が入った時、彩度が高い色が出てくることがある。彩度が高い、というのは蛍光色ということだ。高明度高彩度で光が透過してくる。このようなことが宝石にも起こる。すると高彩度の特性上ポイントカラーが出てくる。その位置は光の反対側に設定するとだいたい合う。
実践に入ろう。前回と順番は同じで透過光を描く。宝石系統を描くときは図形がいくつか重なったような形が見える。宝石の中の色の変化は資料を参考にして描くと楽だが、基本に多角形を分割してそこから発展させよう。キラキラした感じは明度対比から出る。暗い色からすごく明るい色まで、たくさんの明度を混ぜよう。片側に暗い色を入れてみると立体感が出るだろう。宝石の場合、片側に伸びる影が内部に入りやすい。次は正反射だ。ハイライトを入れる。宝石は面が多いので、ハイライトが入る箇所が多い。しかしあまりにたくさん描くよりは一つ一つを大きく描こう。ハイライトの形は照明の形に誘導される。見たときにきれいな形になるように考えながら描いてく。最後に反射光、宝石は球形ではない。角度によって入射角が変わるので解釈の仕方が異なる。反射光は白すぎるよりは、色や形があると良い。(完成)ここからはどれだけ描き込むかによって完成度が変わってくる。よりリアルにしたければ光の屈折率、方向を考慮して高彩度のカラーを光が出る方向に配置しよう。ポイントカラーを散りばめて神秘的な感じを演出することもできる。絵は量の調整が核心だ。ハイライトを削ったり、割ったりしながら描いてこう。
宝石の描き方、宝石の描き方は初心者の頃に悩んだことがある。そのときはハイライトを入れて影を落とせば良い、という風に描いていた。まきあっと先生はそこから一歩踏み込んで透過光の話や光の屈折の話をしてくれたので面白かった。残りは3章だ。
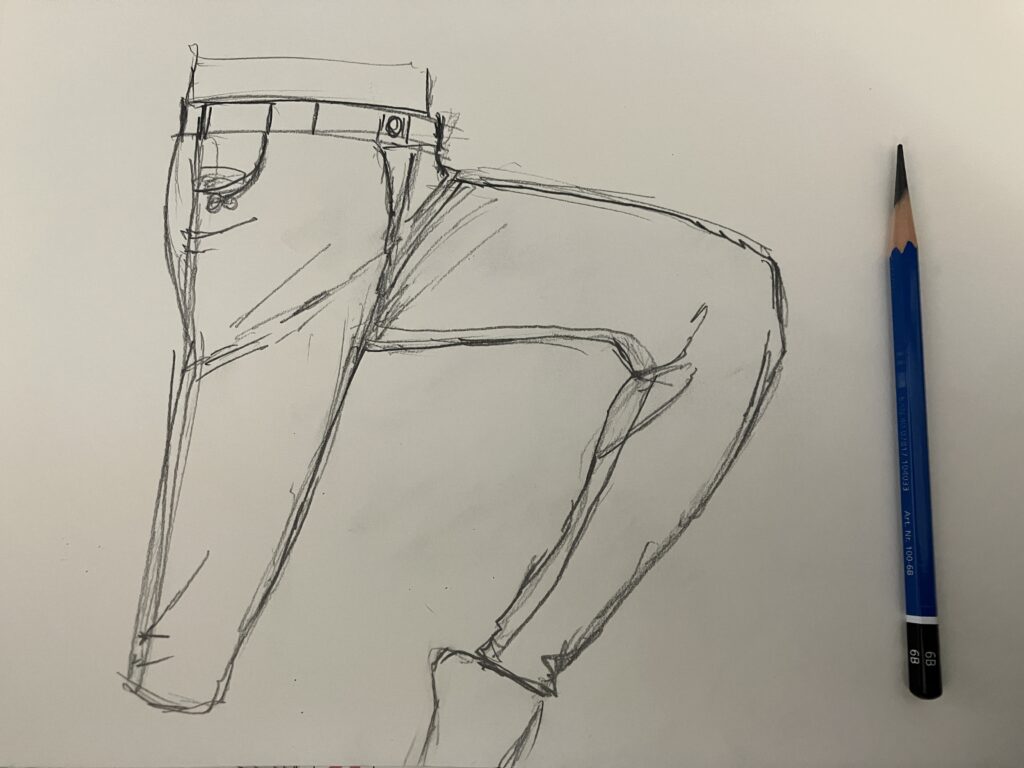



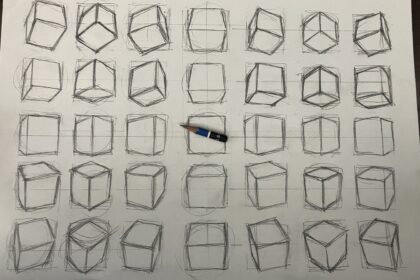


コメントを残す