まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter68_空気遠近法。
主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。
*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より
また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。
後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。
遠近法というのはなんだろうか。遠かったり近かったりするものを表現する技法だ。空気の表現を使って遠近法を応用したのが空気遠近法だ。レオナルド・ダ・ヴィンチが作った。どのような方法で距離を表現するかというと、空気中に存在する様々な粒子(水や塵など)を表現する。遠くにあるほどその粒子が固まって見える。このような大気の特性のため、例えば画面の写真では近くを見ると鮮明に見えるが遠くは霞んで見える。しかし問題は空気遠近法が思ったほど単純ではないということだ。今回はより正確に空気遠近法を表現するために学んでみよう。
よくある誤解の一つに遠くに行くほど青っぽくすれば良い、というものがある。なぜこの青ができたのだろうか。空が青い理由と同じだ。空にもいろんな粒子があるが、波長が短い青色がよく見える。この特性をレイリー散乱という。詳しくは調べてみてほしい。この平均的なカラーで通常青になる確率が高い。どのように青っぽくなるのかは空の色に従えば良い。環境光は本人が決めればよいのだ。つまり環境光は青色でないといけないわけではない。夕焼けの場合は空が赤色だ。あるいはファンタジー要素を入れれば環境光は十分に変わる。あなた自信が設定した環境光のカラーになじませてこそ空気遠近法は効果を発揮する。
もう一つ誤解されている表現として、遠くなると曇るという誤認識がある。ただ灰色にするだけでぼやけるだろうか?遠くなる、曇るということをもう少し詳しく説明すると明度比が低くなる、ということだ。白と黒のボールがありそれらが遠く離れていくとしよう。言い換えると大気の中に埋もれていくと表現できる。環境光は青色の状況でこの青色に埋もれさせていく。すると画面のように変化する。青っぽくなるというのは理解できるだろうが、これが明度比が下がるということだ。暗い色の場合は明るくなり、明るい色の場合は暗くなる、つまり中央値に落ち着くのだ。これをただ単にぼやけると誤解してしまうと全体として明度がおかしくなったり明るい色・暗い色が片方に寄ったりするという問題が生じる。大事なのは明るい色は暗くなり、暗い色は明るくなることだ。遠くに行くほど明度の差はなくなり大気のカラー自体が中央値に抜ける。
一つ実践をしてみよう。近い距離で空気遠近は本来発生しないが美的許容としてキャラクターに空気遠近法をいれる方法がある。例えば片足だけ、など距離感を表現する技法として使える。キャラクターが片足を後ろに引いたときに空気遠近を入れると距離表現できる。大事なのはむやみに入れずに少しだけいれることだ。女子高生がカバンを持っているがカバンの端やスカートの端に空気遠近として優しく包まれる感じを与える。このように簡単に遠近を表現する技法があることを知っておいてほしい。やり方はレイヤーを用意して、背景の色をスポイトで吸い取りエアブラシやブラシで塗り、不透明度を下げる。後ろに行くほど彩度が低くなる性質があるが光のように華やかにしたいならばスクリーンレイヤーを使おう。また背景によっても環境光は変わる。青空の下と室内では光の条件が異なるだろう。section6で光について説明したので詳しくはそちらの方を見てほしい。暗い背景を描くときはスクリーンレイヤーではなく普通のレイヤーで表現すると、空気に埋もれて暗くなる表現ができる。最後に注意点。空気遠近法にあまり頼りすぎないことだ。この空気の遠近の技法は空気がきれいでないことで起こる。空気の遠近を間違って使うと大気汚染のようにも見えかねない。実際に日本の人たちは遠い距離を描くときでも空気遠近を使わない傾向になる。一方で韓国では空気遠近を使う人達が多い。日本のほうが韓国よりも空気がきれいであり、無意識に経験的なものが現れている証左でもある。
section8は遠近法の話だ。遠近法についても学ぶべきことは多いが、こちらについてはある程度知っているのでふむふむ、という感じでサクサク進められそう。日本人が空気遠近をあまり使わない理由は言われてみれば確かにそうかも…と納得した。例えば韓国のモ誰先生はバリバリ空気遠近の表現を使っているがそのような理由があるのかもしれない。
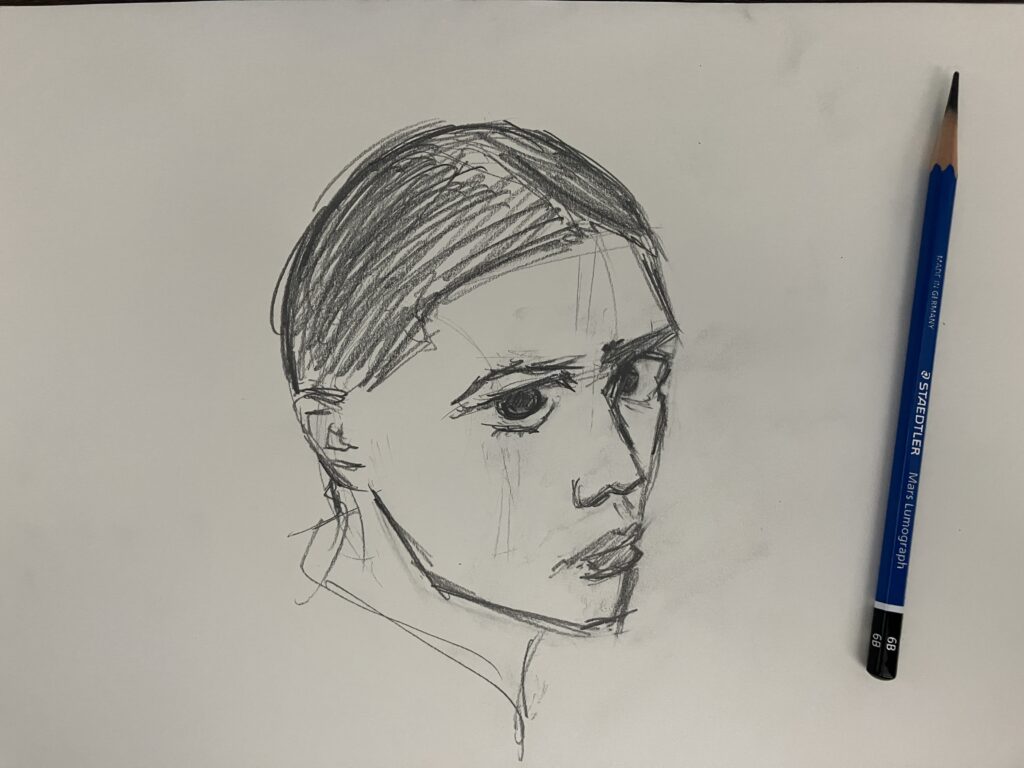
10分くらい。


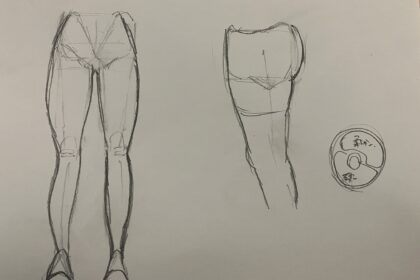
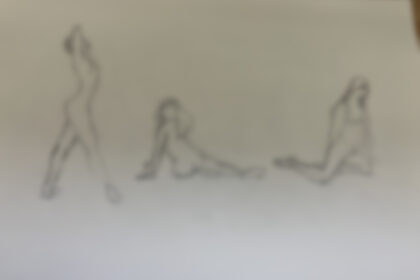
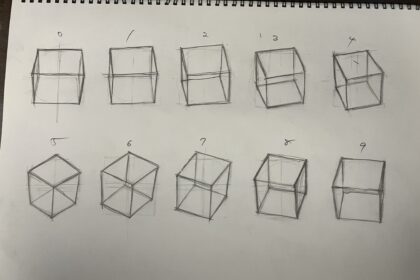
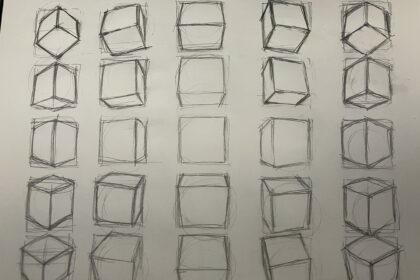
コメントを残す