まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter83_深さを表現する。
主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。
*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より
また講座を受講する順番は、section1→section4→section5→section6→section2→section3→section10→section9→section8→section7を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。
後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。
今日は奥行きの表現について。1点透視で背景を描くとして、中央が収束点、道路も奥に行くに従って収束するとする。間に木があるとして一定の間隔であるとするならば奥に行くに従って密度は濃くなるだろう。ところが多くの初心者の人はここを勘違いしてしまう。手前の1mと奥の1mは全く距離が違う事がわかるだろうか?奥は圧縮されているのだ。空間さえも小さくなっているのである瞬間からは群衆の形に変更される。このように、アイレベルに到達するまでの変化の過程を意識しよう。
視野の歪みが起こる理由。広角では透視線が歪曲する。近くにあるものは更に大きく遠くに行くにつれて小さく見える。私達が実際に物体を知覚するときは球形で捉えている。視野が上下左右縦横に広がってドーム状に視野が広がっているのだ。ところがそれをプロットするときは2次元の格子状で把握する。例えば世界地図(メルカトル図法)と実際の地球儀では大陸の面積が違う。北極や南極に近い位置ほど歪んでいる。そのような理屈が視野でも起こっているのだ。つまり2次元にプロットするには無理やり引き伸ばすしか無いのだ。その結果透視線が歪み、遠い位置ほどそれが顕著になる。
実際の写真を見てみよう。地面の割れ目1マスのサイズに着目。自然物なので全く同じサイズではないが、大きさがほぼ同じだ。手前のマス目と奥のマス目ではサイズがぜんぜん違う。視野角が広いほど縮小も激しくなる。ある一定の距離が離れるとマス目から線になる。更に先に行くと線ではなく面、地面の一部になる。これをどのようにイラストに応用できるだろうか?例えば道路をジグザグに描くと、手前と奥では曲がる間隔が違う。すると視聴者にも伝わりやすくなる。ジグザグが1マスのサイズを伝えるようになる。ポイントは縮小感だ。一定の距離がとれるとジグザグではなく直線になる。あるいは草が生えている間隔が変化したりするだろう。キャラクターにも同様のことが言える。前後の格差を見せれば良い。常識的な部分ではあるが、前に伸ばした手と後ろに伸ばした手を近景と遠景として対比させることができる。エフェクトを加えて大きな流れをを作り近くのものは細かい描写を加えることで対比の演出をつけることもできる。髪の毛や服のシワでも塊の大小を繰り返すことで距離感をつけることができるのだ。
奥行きを演出するにはどのようなことに気をつけるべきかという話。世界地図の歪みの話を聞いて納得できた。やはりsection9は最初の頃に受けるべきだったかもしれない。
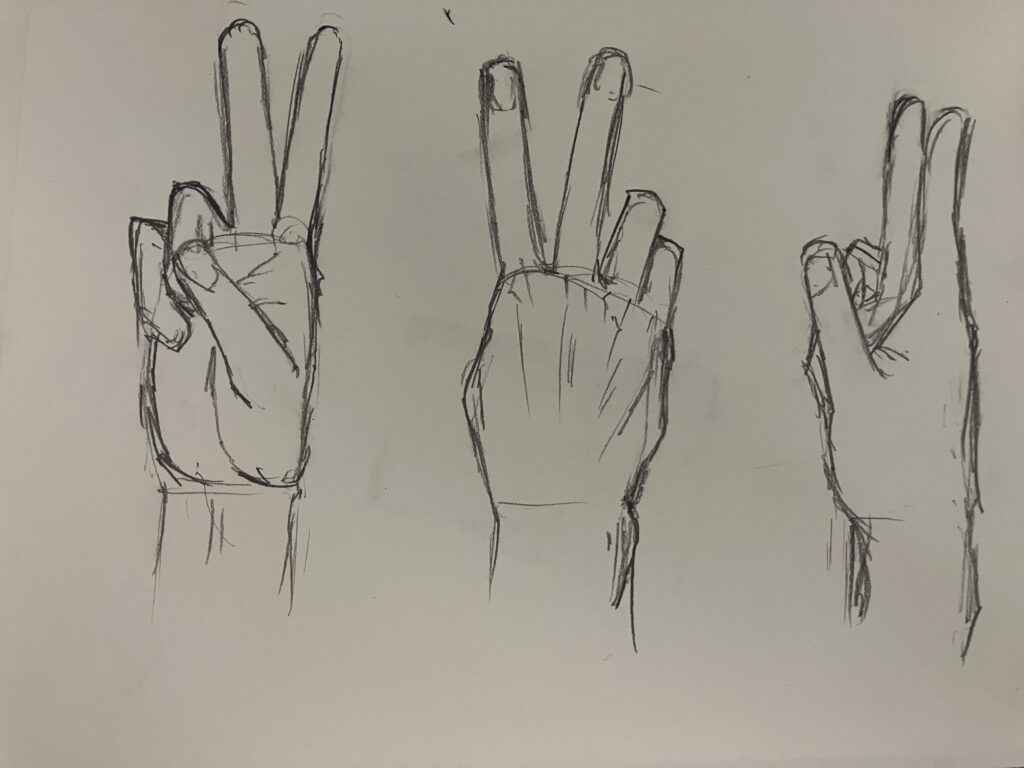




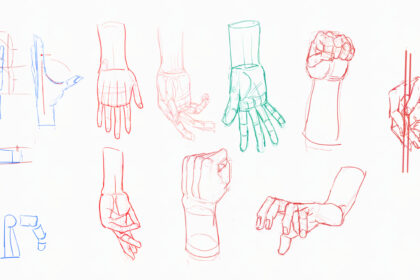
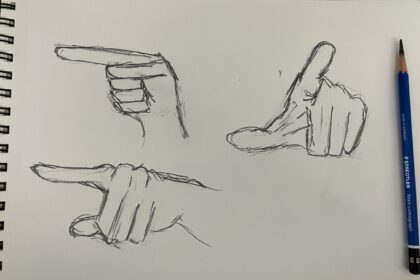
コメントを残す