まきあっと先生「スランプから抜け出すカジュアル風イラスト秘訣ノート」(全100講 49時間 12分)を購入したので消化していく。今回はchapter78_消失点を理解する。
主に人体ドローイングの作品はそのままアップしていることが多いが、それ以外のノート等には一応モザイクをかけている。というのも、「作品」はアップしていいよとcoloso規約*に書いてあるが、それ以外については書いていないからだ。深読みしすぎかもしれないが、「作品以外については」アップするなと読むこともできる。つまりそこら辺はグレーゾーンなので深く立ち入ることはしない。モザイクをかけたノートに意味があるのかは分からないが、どちらかというと私自身の寝落ち防止&モチベ維持の意味が大きい。その点はご容赦いただきたい。
*各講座の講座資料「講座資料、提供ファイルの取扱について.pdf」より
また講座を受講する順番はsection1⇢section4⇢section5→section6を予定している。※section11(93章から100章)のみ各sectionが終わったタイミングで都度、受講する。飛び飛びになるがご容赦頂きたい。
後はあまり詳しく書くとなんか言われそうなので以下メモ書き程度。
本格的に透視の話。この講座を聞く方の中には既に透視を学んだ人がいるかも知れない。その透視を学んだことはイラストに役立っただろうか?ほとんど役立たなかったかもしれない。透視を学んだにも関わらず本質的に何かを阻まれている感じだ。グリッド、消失点の表示線を引いて構造化して完成させたとしてもなにか不自然なものを感じた人は多いだろう。透視は現実を理論化しながら物理的な数学的な方向から空間を解釈する。情報量が減り、物体と物体との距離感や空間が要約されて現実の受け取り方とは異なるのが原因だ。そのため透視理論だけで描いていると少し物足りなくなる。結論を言うと透視理論以上に空間認知能力が重要になってくる。空間認知能力があると透視が簡単になる。しかし透視理論だけで空間認知能力まではカバーできない。空間そのものを理解していない透視は理解していないのと同義だ。残念ながら空間認知能力は才能の範囲内で生まれつき差があるが、後天的に伸ばすことも可能だ。今回は単純な理論を超えて空間認知能力を育てるためにはどうすればよいのか話そう。例えば数学の問題を解く時に、公式を知っていればある程度の問題を解くことができる。しかし本質的に理解するためには公式について理解できないといけない。空間認知能力の話は数学の話に似ている。そのためある面ではとても簡単に感じられるが、本質について(空間について)理解するためには時間がかかるし骨も折れるだろう。
透視理論とはなんだろうか?一言でいうと「遠くなると小さく見える」ことだ。遠くにある物体はより小さく見える。これが透視理論の基本だ。それを覚えている状態で消失点という単語にアプローチしよう。3Dの空間がある。3本の線が平行にある。この線は数学の世界では(理論的には)永遠に合うことはない。しかし現実の世界では違う。ずっと伸ばしていくと1箇所に向かって線が走っていく。1つの点で集まるようにみえる。これは空間が遠くなるほど小さく見えるからだ。この点を消失点(VP)という。小さくなって点となる。しかし注意点がある。平行線ということだ。平行でない線は交わらないのだろうか?答えはYESだ。私が言いたいことは平行でなければ同じ点に集まらないことだ。絵画の中ですべての線分を1箇所に集めようとするケース、例えば建物が沢山あって画面の真ん中のVPに集まっているように見える絵があるだろう。しかし上から見るとすべての建物が平行に建てられている必要がある。このような状況が作為的に見えてしまい、違和感が出てくるのだ。あるいは机の上にあるスマホやノートを1点透視で描こうとすると、すべてのモノが規則的に正しく並べられている必要がある。このように背景の中に描くすべての物体を1つや2つや3つに収束させようとすると作為的な感じがするのだ。実際は無数の消失点が存在する。多様で多くの消失点が空間に形成されているのだ。ここを勘違いしないようにしよう。1点透視や2点透視は代表的な線を収束させるに過ぎない。もう一つ話そう、消失点が2つある。この地平線はアイレベルという。このように真ん中にアイレベルを引いて消失点を設定すると地平線に消失点があると思いがちだが違う。面はいくつかの線で構成されている。みなさんがアイレベルという真ん中の線に気をつけなければならないことは知っているが、手前に坂があったりして線が上や下に移動することもある。するとこれらの線はアイレベルの線には収束しない。アイレベルに収束するのは地面と平行の線や面のみだ。
1点透視や2点透視3点透視という言葉について、自然なイラストを描きたいのなら3点透視以上を狙うべきだ。1点透視や2点透視はゲームで言うとイージーモードのようなもので透視についての概念を理解するための過程に過ぎない。俗に言う人体図形化は3点透視のアプローチだ。私達が住んでいる世界は3次元の世界で、これを3次元空間という。結論的には六面体を上手く描くことができれば空間を演出できる。1点透視や2点透視はあくまで限定的な場合にのみ適用できる。個人的には3点透視、つまり立方体についての練習をすることを勧める。
久しぶりの更新、タイミングが若干ずれていたがお盆休みのようなもので、今日から更新再開となる。この章は空間やパースについて学んでいくための前座的な位置づけだ。透視については学んできたが、最初の導入部分がしっかりしているのがまきあっと先生のいいところだ。空間認知能力は一朝一夕では身につくものではないので日々練習していきたい。
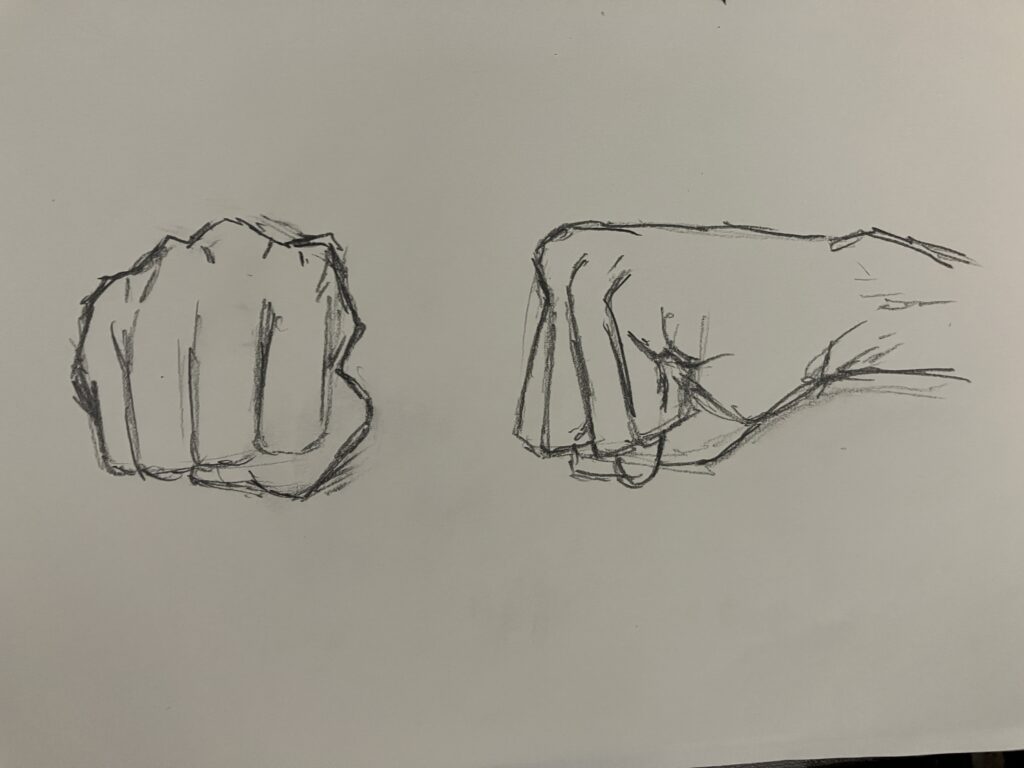



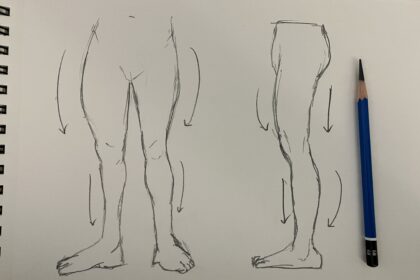
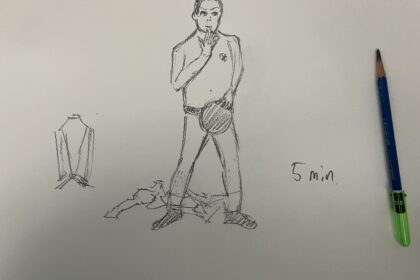
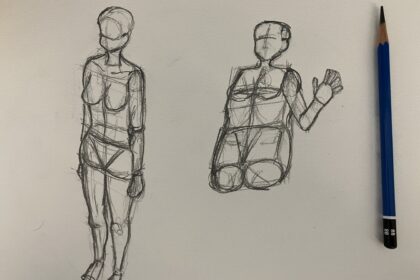
コメントを残す